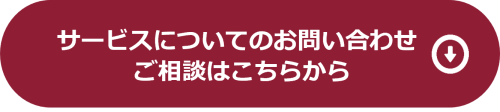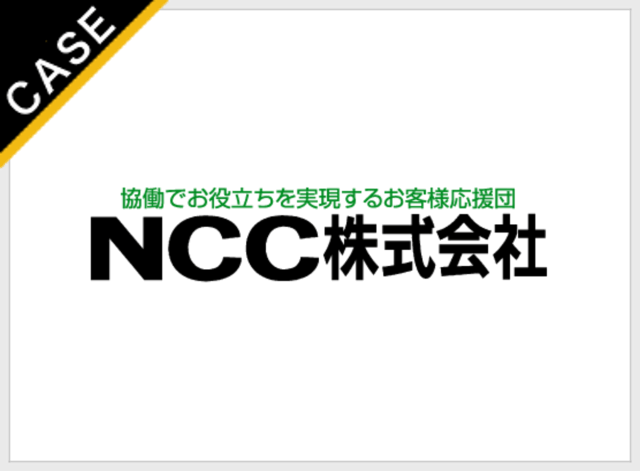7つの習慣®研修とは
7つの習慣®研修の目的
優れた人格や人間性を備える
スキルを磨き、優れたビジネスマンになることは重要です。ですが、その前に人格を磨き、優れた人間になることはもっと重要です。
なぜなら、スキルは、どのように使うかに価値があり、正しく適切に使うためには、優れた人格や人間性が備わっている必要があるからです。
継続的な成長
人は目の前の成果ばかり求めがちです。しかし、目の前の成果と同時に、成果を生む能力も磨きつづけなければ、いずれ成果を得ることはできなくなってしまいます。
成果と能力のバランスを保ち、効果性を高めることが、真の成功には不可欠です。7つの習慣®を取り入れることで継続的な成長が可能となります。
得たい成果を得続ける
「得たい成果そのものに対して」、「得たい成果を生み出すために必要な資源や能力」があり、2つをバランス良く向上させることが「成果を出し続ける」ためには大切です。
人は目の前の成果ばかり求めがちですが、目の前の成果と同時に、成果を生む能力も磨きつづけなければ、いずれ成果を得ることはできなくなってしまいます。
7つの習慣®を取り入れ、成果と能力のバランスを保ち、効果性を高めることが真の成功には不可欠です。
7つの習慣®研修のポイント
7つの習慣®では、まずは基礎原則、そして7個の習慣がどのように関連しているのかを示す「成長の連続体®」という概念が重要です。
基礎原則を学ぶ
7つの習慣®には名前の通り、人格を磨く7個の習慣が解説されています。これは単に7個の習慣を箇条書きにしているわけではなく、各習慣を学ぶ前の入り口となるので、「基礎原則」と呼ばれます。
- 基礎原則①「インサイド・アウト®」
- 基礎原則②「パラダイム®」
- 基礎原則③「パラダイム・シフト」
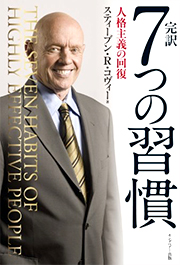
成長の連続体を学ぶ
7個の習慣がどのように関連しているのかを示すものが「成長の連続体®」という概念で、これは人間性のステージを3つに分類します。
- 「依存」
- 「自立」…私的成功®
- 「相互依存」…公的成功®

7つの習慣®研修でこんなお悩みがありませんか?

言われたことしかしない社員がいる

問題を起こしている“キー”となる社員の方をご派遣ください!
翌日からすぐにガラッと変わるかどうかは、人によります。ですが、この2日間研修がご参加いただいた方の記憶にくさびを打ち込むことになるのは間違いありません。
この2日間研修は、何かを強制してやらせるようなセミナーではなく、自身の中にある潜在的なニーズや、仕事を通して本当に成し遂げたいことを浮き彫りにし、本人が心からやりたくてワクワクするようなことを軸に、お伝えしていきます。

社員から主体性を感じられない

主体性の大切さを学びます!
「こんな職場で何か新しいことを提案したところで、どうせ無駄だ」と考えている人がいるとします。その人は「新しい提案が生まれない原因は、職場にある」と考えているかもしれませんが、個人毎で考えると、新しい提案をしていないのは、あくまでその人自身であり、問題の原因を外に求めてしまっている、ともいうことが出来ます。
「主体性を発揮する」という習慣では、
「問題の原因は外にあると考えているのであれば、その考え方こそが問題である」
と伝えています。

組織の雰囲気が悪い

「まず自ら、相手を理解しようとする」ことの大切さと、その具体的なスキルを学んでいただきます。
「まず理解に徹し、そして理解される®」この習慣を学べば、参加者は相手のことを理解しようと自ら進んで動き始めますし、その姿勢を感じた周囲の人々はその人に対して、厚い信頼を置くようになります。
そうすれば、貴社の風土は好循環をし始めるようになるのです。
ジェイックの7つの習慣®研修
主体性を学ぶ
第1の習慣では、自ら行動を選択し、責任をもって自分の人生を生きるためということを学びます。
人間は生まれつき、刺激に対してどのように反応するかを選択する力を備えています。
刺激と反応の間にスペースを置くことで、私たちは自らの行動や態度を選ぶことができるようになります。
この「一時停止して選択する」ことこそが主体性です。
私たちは自らの人生を自分の意思でつくることができます。
- 第1の習慣「主体的である」

相手のことを理解し、相手の望む結果を知ることを学ぶ
第4の習慣のWin-Winの関係を築くには、まず相手のことを理解し、相手のWin(望む結果)を知ることが不可欠です。
しかし、私たちはまず「自分のことを分かって欲しい」と振る舞ってしまいがちです。
相手の話を聞くときにも、相手を評価したり、自分の経験で解釈したり、といった形で自分本位な聞き方をしがちです。
これでは、相手を本当に理解することはできません。
誠実に相手の話を聞き、相手の立場になって、徹底して相手を理解しようとする姿勢を学びます。
- 第5の習慣「まず理解に徹し、そして理解される」

カリキュラム例
- 1日目 10:00~18:00
オリエンテーション
- はじめに
- 7つの習慣®の目的 ~イントロダクション~
- 効果性を高める活動
基礎原則
- 効果性のルーツ
- インサイドアウト®
- 成長の連続体®
基礎原則
- See-Do-Getサイクル
- パラダイム®
- ガチョウと黄金の卵
第一の習慣
- 自分の天気を持つ
- 一時停止 ~刺激と反応~
- 影響の輪®、関心の輪®
第二の習慣
- 終わりを思い描くことから始める
- 自分だけのミッションステートメント
- あなたに捧げる言葉
第三の習慣
- 時間管理のマトリックス®
- 日頃から行っていれば
エンディング
- 振り返りとまとめ
- 宿題 ~最後だとわかっていたなら~
- 2日目 10:00~18:00
前回の振り返り・オリエンテーション
- ミッションステートメント
- 公的成功®
- 信頼残高
第四の習慣
- 人間関係の4つのパラダイム®
- 勇気と思いやりのバランス
- ソーシャルタイプ診断
第五の習慣
- ワードゲーム
- 傾聴の5段階
- 同僚をどれだけ知っているか?
第六の習慣
- 相乗効果
- コップの使い道
- 裸の男とリーダーシップ
第七の習慣
- 刃を研ぐ®
- 21日間行動の設定
エンディング
- 宿題解説と、全体のまとめ
受講者の声

チームの人間関係が変わりました
部下との関係がイマイチうまくいっておらず、自分の考えと異なる言動があるとついイラッとしてしまい、態度に出がちでした。
パラダイム・シフトの重要性を学び、部下に対して「自分よりもいいパラダイムがあるかもしれない」と考え方を変えたことで、以前よりもコミュニケーションが取りやすくなり、チームの一体感が増した気がします!

研修を受ける事で、自分に足りていない部分に気付くことができました
リーダーとして何をすべきか、何を目指したらいいのか、ぼんやりとしか考えていなかったのですが、この研修で自分に足りない部分に気付くことができ、挑戦したいこと、今後やりたいことが明確になりました。

上司に「変わったね」と言われました
自分自身としてはこの研修を元に、少しずつ行動を変えただけだったのですが、上司には「部下との関わり方が良くなった」「より成果に直結する仕事ができるようになった」と言われました!
7つの習慣®研修 実施までの流れ
お問い合わせ、資料請求
Webサイト、電話などでまずはお問い合わせください。研修の概要をご説明し、資料をお送りいたします。
「何日かかるの?」「平日と土日どっちがいい?」「何人まで参加できる?」といった細かいことからお気軽にお問い合わせください。訪問・お見積り、内容の決定
担当者が貴社に訪問し、具体的な日程、時間、内容を貴社に合わせてカスタマイズし、提案いたします。
日程と内容が確定しましたら、講師を選定し、見積額を提示いたします。
「どんな講師が登壇するの?」「社員への事前アナウンスはどうする?」など、不安なことはすべて担当者にお尋ねください。研修実施
研修前に最終確認として、参加者名簿をご用意の上、弊社に共有ください。研修当日は会場に直接、講師が伺って設営をおこないます。
準備が終わると、いざ本番!ディスカッションや模造紙ワークを中心に進行します。
始めや休憩、終わり頃にぜひ見学いただき、参加者の変化を感じてください。フォローアップ
研修後、現場に帰って日常業務に戻ると、研修での学びや気づきが薄まってしまいます。そこで弊社では、研修後も継続して学びが浸透するよう「習慣化プログラム」を用意しております。
また、研修実施報告のための訪問をおこない、登壇した講師から、貴社の社員一人一人に合った指導方法をアドバイスいたします。
7つの習慣®研修でよくある質問
一度に研修を受けられる人数に制限はありますか?
1開催30名を目安にご検討ください!
対象社員はどの層ですか?
若手社員・中堅社員・管理職等どの階層向けでもカスタマイズ可能ですので、ご気軽にお問い合わせください!
リアルでの研修も実施できますか?
貴社のご状況に合わせて、リアルでもオンラインでも実施可能です。こちらも是非、ご気軽にお問い合わせください!